「畝葉逗柳(うねばとうりゅう)だぁ?」
白棒を立てる手を止め、声を上げたのが、我が友人、橿井治である。
このゲーム中において、彼の唯一のミスのある動きだった。
「おう、知ってるか。G5」
改めて白棒を立て直し、すぐに視線を上げ俺の顔を見つめる。
「ミス、F8。知ってると言っても名前くらいだぞ。俺たちが生まれる前のSF小説家だったか」
ボードを見やるとそこには巡洋艦が浮かんでいる。
「ヒット、F5。それだけ知ってれば十分立派よ」
俺は切り出した会話を続ける。
これは黙っていると、情勢が顔に出てしまうのを防ぐ為の策だ。そうでもしなければ俺は治に勝てない。実際のところ話題なんてどうでもよかったし、これを治に教えるつもりはなかった。
「その畝葉の屋敷ってやつを俺の大学の時の友人の親が買ったらしく、招待を受けたわけ」
だが、今、俺の手札にあるカードの内、一番、治の興味を引けそうな話題だったのがこれだったのだ。
治の顔を伺うがすでに冷静そのもの、先ほどのような醜態を今一度見ることは難しいだろう。
「ミス、F4。よくもまぁそんなマイナーな人の屋敷を買ったな。親はSF好きかなんかだったのか?」
「ヒット」
極力、舌を回し続けろ。視線は動かしてはいけない、きっとボードに目を落としている今でも彼は俺の眼をジッと観察し続けている。
「さぁ、親のことまでは知らないなぁ。そいつはスターウォーズも見たことないって言ってたし、そういう趣味はなかったと思うが、えー、I2」
中央付近は埒が明かないので隅を狙う。どうだ。
「ミスだ、F3」
表情に変化は見られない。
「ミス、じゃあB2で。それで招待されたはいいけど、なんにも知らない俺が行くくらいならお前も連れて行こうと思ってな。今週末、暇か?」
「ミス、F6。暇だけど、俺だって畝葉逗柳なんてしらないぞ」
「沈没」
大きく舌打ちをする。奴に動揺させ、かつ、俺の同様を隠す為の会話だったが、全然、効果はなかったようだ。いや、あったのだろう。彼にしてはこの話、なかなか食いつきが良い。
「B9。じゃあ行かないんだな」
口調は断定的に、煽るように。
大体からして、高校時代から俺はこのゲームの勝率が悪い。どうすればもっと勝てるのだろうか。きっと治相手にしかやってないことが原因だろうけど。
「ミス、D4。そうは言っちゃいない。行くに決まっているだろう」
ヒットだ。
「それならうだうだ言うなよ。じゃあ、俺は帰るから。土曜の九時に俺んち来てくれ」
俺はゲームを放り出して、立ち上がる。
「あ、お前、まだ途中じゃねえか」
ボードを指さし俺を静止するが、立ち止まるつもりはない。このまま続ければ俺の負けだ。
「夜も更けてきたし、連絡やらなんやらがあるんでな。またな」
これで、俺の心のノートに記された勝率と治の紙のノートに刻まれた勝率に食い違いが生じるだろう。しかし、信じるべきは己の心。やつが十年前からすべてのゲームの記録を取っているとしてもそれがなんだというのだろう。
サザエさんも終わりそうな星の夜であった。
普通自動車にまとめて詰め込まれ、郊外に連れ出される一行。
運転手を務めるは小鹿壮二。俺とは大学の学部学科も一緒で、すでに畝葉邸に行ったことがあるという。
他のメンバーも俺にとっては顔なじみばかりではあるが治にとっては初対面ばかりのはずだが、それに臆することなく平然とした顔でいるのは、決して社交的な訳ではなく、他人への興味が薄いだけだ。普段から奴はわけもなく集まろうと声をかけると無視をする。
「お前、随分と眠そうだな」
しかし、彼もまた社会人になったからなのか、学生時代にはなかった社交性は身に着けているようだ。瞼が落ちそうなほどトロンとしているのに耐えているのは、さすがに配慮といってよいだろう。俺と二人だったら確実に寝てる。
「ああ、まぁな。畝葉逗柳邸に行くに当たって有名どころには目を通してきたんだ。さすがに時間が足りなくて二冊しか読めてはない」
治の会社はホワイト企業である。だから平日の夜、時間がある。俺にはない。だから俺はそんな時間を取ることができなかった。そういうことにする。
「そりゃまた結構な心がけで。今日、来る奴らの中でお前が一番、畝葉先生に詳しいだろうよ」
畝葉逗柳という人物が目的で今日の集まりに来た者はおそらくいない。そういう意味ではこんな闖入者を連れ込んでよかったものかと思うのだが、そもそも俺自身あまり来る気はなかった。ポーカーフェイスを保つための話題として提供しただけなのだ。そして、俺は治と一緒に来ることを「興味がある友人がいるから一緒に行ってもいいなら行く」と伝えている。ここまで思い返すと、全て自分都合で話をしていることに気付く。そしてこれは一歩間違えば誰も幸せにならない結末すらありうる。今更ながら不安になってきたが後の祭り、すべて自分の蒔いた種。
「ねえねえ、結局、畝葉逗柳ってどういう人なの?」
そう言って顔を出したのは、我々と一緒に後部座席に押し込まれている柿崎景。なかなかの美形でスレンダーな体型からガッキーとかけてカッキーというあだ名を頂戴している。このあだ名を使う人間の中には「ガッキーには一歩及ばない」という皮肉を込めていた者もいたが、トップ芸能人に並び立つ人間がそうそういてたまるか、と俺は思う。偶然にもその彼女が隣に座っているというだけで、今日はツイている。
「俺も為人は知らないんだけど畝葉逗柳っていうのは、」
「畝葉逗柳は日本のSF作家。○△県□×市生まれ。1970~0年代のSFブームに活躍し、代表作は「湖の鏡」。鏡をモチーフに作品が多く、別宅には道路側から見える鏡の間(ミラーハウス)を作っている。「美良の時」は1981年に映画化され、畝葉唯一の映像化作品となる。2008年没」
治を遮って、読み上げるように応えるのは助手席に座っていた浮田翔子。
「それも、wiki情報か?さっそくwiki田だな」
運転席から声がする。浮田はwikipedia信者であり、常日頃から誰かの疑問に対し、いち早く検索しwiki情報を伝えることを生きがいとしているように見える。wikipediaの寄付広告に対し、実際に寄付をしている人間に浮田以外会ったことがない。wiki田とはお分かりの通り彼女のあだ名だ。彼女の存在のせいで我々仲間内では学生時代、検索をするという習慣がなかった。
「そのへんの情報は俺は全く知らなかった。あくまで俺は作品を読んだだけなんだ。しかし、読んだのはそこで出てきた湖の鏡と美良の時だね。湖の鏡は湖の底に沈められた鏡と湖の表面とで合わせ鏡を作りだし、そこに多重世界を構築するという話で、そこから這い出せるかというのが大筋なんだが、確かによくできていた。その点、美良の時は湖の鏡より後年の作品なんだがちょっと独創性に欠けるというか焼き直し感がある。しかし、映像化はこっちの方がし易かったんだね、きっと」
「ふーん、あの鏡の間にはそんな意味があったのか、あれは結構見ごたえあるぜ」
wikiに名前があるあたり、畝葉逗柳氏は割と有名なのだろう。もっとマイナーかと思っていた俺は内心驚いていた。
しかし、単に乗せた順番なんだろうが、助手席に浮田が座っているのは妙な感じがする。普通に考えたら、男としては柿崎を隣に座らせたいと思うだろう。決して浮田が可愛くないと言っているわけではないが、柿崎に比べると格落ちというか、なんというか。それが柿崎は挟まれていないだけマシかもしれないが野郎二人と一緒くたにされている。もしかして、小鹿は浮田に気があるのかしらん?と勝手な想像をしてしまう。
そんなこんなで旧友を深めつつ、郊外を二時間ほど走ったところで、車の外は鬱蒼とした木々に囲わてきた。虫が多そうだという考えがチラついたところで、
「なんかすっごい森の中に来たね。マイナスイオンを感じる」
と右から意見が出る。なるほどそう意見すればおしゃれなのかとつまらん感動をしつつ、マイナスイオンの存在に懐疑的な俺は左で結局、一時間を超えたところで会話にも混ざりきれず睡魔とランデブーした治を起こそうとする。
「マイナスイオンはニセ科学、未科学とされ、効果は未判明」
スマホに目を落としたまま、答える浮田。そういう答え方は角が立つが、慣れているのでどうってことはない。wikiは俺の味方なようだし。
「マイナスイオンがどうだって?」
やっと目を覚ました治が耳の端に捉えた単語に反応する。
「ああ、すっかり森の中にいるじゃないか。つまりそれは森の中に来たからマイナスイオンがでているだの、そういう話だね」
誰に言われずとも状況把握を始める。一を聞いて十を知る彼は便利なのことこの上ない。こいつと俺と通った大学が違ったのは単に治の頭に俺がついていくことができなかった為なのでそういう意味で頭の出来が違うのである。
「いいじゃないかマイナスイオン。科学的に何か意見いう必要はないよ。俺達は専門なわけではないし、確かに似非科学かもしれないが、それほどにまで意図をもって森林をマイナスイオンと評したわけではないだろう。なんとなく癒し効果がある、くらいの意味合いで世間一般の表現としてマイナスイオンという言葉を選ぶのは正否は別として普通のことじゃないか、目くじらを立てる必要はない」
そう言って、俺の方を見つめる。
「俺はまだ何も言ってない」
こいつは何も言っていない俺に無実の罪を着せようというのか。
「違うのか。てっきり、お前がいらんこと言って女の子達から顰蹙を買っているのかと思ったが」
一を聞いて十を知るというのは十がまだ実行されていない場合、未来予知となる。顰蹙を買う未来をここで食い止めてくれたと考えればそれも治と親切だと考えよう。
隣で漫才をボーっと見ていた柿崎は、
「お二人は仲がいいんですねえ」
などと言い出す始末。否定はしないが、ここでイエスと答えると変な意味に捉えられかねない。
「もう少しで着くぞ」
カーブに差し掛かって小鹿が言う。森の中に近代的な屋根がチラリと見えてきた。
畝葉邸の外形は一見妙な形をしていた。三階建てのようだが、道路側から見た時、右半分は一階、二階、三階がすべて存在しているようだが、左半分には三階部分しか存在しない。左半分の一・二階部が正方形にくり抜かれ、三階部分だけ全体にかかっているのだ。個人的にはひどく無駄に感じられるが、これがデザインというものなのだろう。
道路側ということは、と鏡の間を探していると、
「ミラーハウスは一階だよ」
と言われる。ということは、くり抜かれていない右側の一階部分がそれか。窓があるのはわかるが、周りは背の低い木々に囲まれ遠目では中を覗くことができない。
既に停めてあった車の隣に小鹿は車を停める。
駐車スペースの背後には階段があり、玄関は右の二階に当たる部分にあった。
完全にくり抜かれていると思ったのだが玄関への階段があったり、さらにその奥には壁があったので益々、構造がわかりにくくなる。
インターフォンを押すと畝葉邸の主がドアを開ける。
「いらっしゃい。わざわざ遠くまで悪かったな。その分、家の中身はなかなかなもんだぞ」
歓迎してくれたのは件の友人、畝葉邸の主、灰田雅紀。
「よう、久しぶりだな、畝平」
そして、畝葉逗柳の苗字と文字が被っているという理由で今回、久々ながら声を掛けられた畝沢一平こと畝平が俺。今回の登場人物は以上となる。
玄関から入ってすぐの部屋のリビングは非常に広くこの階の全てのスペースを使用しているようだった。そして、中央にやけに太い柱があるのが印象的だ。人が三人ほど手を繋いでやっと一周できるくらいだろうか。調度品は至って普通であり、これが畝葉逗柳の趣味なのかそれとも灰田家が後から買い足したのかはわからない。
灰田は人数分のコーヒーを入れて並べた後、ソファに腰を下ろす。長いこと車に揺られた疲れから、はじめは休憩と大人しくしていたものの、少し回復すればすぐに意識はアレに移ってしまう。
「なぁ、鏡の部屋を見てみたいんだが」
おもむろに口を空けたのは治だった。それに釣られて、俺も私もと皆、声をあげる。
「そうか、そうだね。畝葉ファンとしては当然見ておきたいよね」
灰田から向けられた視線を反射するかのように飛ばす治。仕方がなかったのだと目で訴えるが彼のことだ。すべてもう理解しているのだろう。
「そうだ、女性陣はスカートじゃないかね」
女性陣は二名。浮田はスカートで、柿崎は七分のパンツだ。
「いや、セクハラではなくてだな。鏡の間は流石というべきか、床まで鏡なんだ。だから、スカートだとパンツが見えてしまうんだな、これが。僕はそれでも一向に構わないのだが、一応は紳士的に振舞おうというわけよ。ほら、僕のジャージですまないがはいてくれ」
がさごそとクローゼットを漁ると紺に白のラインの入ったジャージのズボンが出てきた。綺麗に畳まれており、清潔感はある為、浮田はそれを抵抗なくはいていく。
「俺は前見たからいいや」と同行を拒否した小鹿を除いた五名がぞろぞろと部屋を出る。
「おい、鏡の間は一階じゃないのか?」
先導する灰田は階段を上がろうとしている。
「そうだよ。だが、この家はなかなか複雑でね。大体見てみろよ、ここに下にいく階段はあるか?」
部屋を出て正面に見えるは玄関ドア、その左に上へと続く階段があり、確かに他にはなにもないようだ。
割と長めの階段を昇ると、つまり、駐車場上の空間に当たる場所はダイニングになっていた。調理器具や簡単な調味料等は揃えられているようだ。普通に家としての機能も持たせているのだろう。また、昼ごはん用に用意されていると思しき、調理済みの料理と酒、菓子類がある。
リビングの上に当たる部屋は二部屋に道路側とそうじゃない側で二部屋に分離しており、寝室となっている。
そして、二階にもあった大きな支柱は三階の天井まで続いているが床から人の身長より一回り大きいくらいの高さで前後にパックリと口を空けており我々を飲み込もうとしている。その正体は螺旋階段だった。
「なんで、こんな構造にしてまで螺旋階段を作ったのかはわからないんだけどね。単に長い階段を作りたかったのかな。ほら、この家って天井も高いでしょ?」
天井の高さなんてものは今まで意識したことがなかったが、先ほどの階段も長いと感じたのは間違いではなかったようだ。
「現実感をなくしたかったのでは。一度上に昇ってから再度下がらないといけない。そして暗闇の空間を挟むことで現在地を不明確にし、辿り着いた場所は異世界へとつながるという要素をここで表現したかったのではないだろうか」
「なるほどね。父さんも構造も気に入ってたようで、でも決め手はやっぱりこの部屋でしょう」
階段を下りきった先も三階と同様、部屋は二つに分かれていた。

その内、片方のドアノブを回すと、一面の自分達の姿が見える。
鏡の間だ。
単に四隅を鏡張りにしているわけではなく分割し、角度をつけることであらゆる方向へと反射をし、無限の奥行きを醸し出している。
この部屋の徹底振りは見事なもので、聞いていた通り床も鏡なら天井も、そして、ドアの裏側までもが鏡になっている。見渡す限り全てが鏡の海、いや、湖で、異物があるとすれば天井から吊り下げられた電灯だけだが、それも夜に照らせば辺りの鏡に反射し、さぞ美しいことだろう。
「外から見たとき、窓があったように思えたんだけど」
「外?ああ、窓はね、ここだ」
灰田はドアから見た正面の壁を指さす。よく見るとサッシと簡易鍵のようなものがあり、光の反射の仕方も鈍いようだ。
「これは特殊なマジックミラーになってるんだ」
光の強弱に関係なく外からは覗くことができるが中からは外を見ることはできないようになったマジックミラーだそうだ。MM号の反対の構造になっている。
「すごく無意味だと思うんだが、ここまで徹底すると圧巻だよ」
「ジャージ借りてよかった。これじゃあ、どこを向いたってパンツがみえちゃう」
浮田がそう呟くと、皆はドッと笑った。
もう一つの部屋は物置だというので一応、覗かせてもらったが掃除機やらが置いてあるだけだった。
そして一行はリビングへと戻る。
「おかえり、鏡の間、なかなかのもんだっただろ?」
「なんでお前がそんな偉そうなんだ」
そんなことより腹が減ったと、リビングで退屈を持て余していた小鹿は言い出す。たしかに十二時を回り、そろそろお昼時だ。
「じゃあ、上から昼ご飯を取ってくるね」
と、柿崎は部屋を飛び出そうとするが、灰田がそれを止める。
「いや、全員で上へあがろう。運ぶには量があるし」
「お、なんだ?上に用意してあるのか。気が利くね。まあ、食いに出るにしても随分と行かないといけないからそりゃそうか」
そう言って、一行は腰をつける間もなく、移動を始める。俺は今後の状況を予想し、カバンを持って行くことにした。
食事はピザやサンドイッチといった手軽に食べられるもので食べながら、ハンドルキーパーではない小鹿以外は酒もドンドン空けていく。
そうするとトイレにも行きたくなるもので面倒なことにこの家のトイレは階段の先にあった。つまり、一度、階段の入り口を潜って階段を踏み、出た先にトイレのドアがあるのだ。ここまでしてこの螺旋階段に拘りがあったのだろうか。
トイレから戻ると早速、治に尋ねてみる。
「なぁ、さっき階段を出た先が異世界だと言ってたけど、あの支柱が上にも伸びているのはどういうわけだろう。トイレに行くのに非常に面倒なんだが何か、それほどにまで階段という空間を長くすることに意味があるのだろうか。あと、一階が異次元と繋がるというのにしては物置があるってのはどうなんだろうか」
「さて、天井にも柱が伸びているか。この家には屋根裏部屋でもあるのでは」
「残念だけどないよ」
家主が口を挟む。
「それに一階の部屋はもともと物置ではなかったんだ。三階の寝室の内、一部屋が物置となっていて、あの部屋は畝葉逗柳本人の寝室だったらしい。橿井くんの言葉を借りると異次元世界で彼は寝泊りしていたことになるね。きっといい夢が見られたんじゃないかな」
とすると自分の美観を優先し、便利さは二の次の設計だったことになる。
「天井に繋がっているというのはこの階段は天界にも通じているという暗喩だったのかもしれないよ。限りがなければ想像は自由だからね」
「ふーん、SF作家様が考えることはよくわからんよ。こんな家建てる余裕がよくあったね」
「家が金持ちだったんだ。作家としては所詮マイナーだからね。むしろ小説は金持ちの道楽程度のものだったんだろう」
「それは益々羨ましいことで」
その家をポンッと買える灰田家も金持ちなわけで羨ましいったらありゃしない。
「それよりも畝平、お前どうせなんか持ってきてんだろ?」
食事も満足し、話に飽きてきたのか小鹿は声を掛けてくる。
俺は特に意味もない会話だけで夜まで過ごせるほど口達者な人間でもないし、聞き上手でもない。しかし、世の中にはそれだけで時間を潰そうと目論む輩は予想外に多く、大学入学当初は軽いショックを受けた。始めのうちはまだいいが、途中からぐだぐだして来て、はっきり言って誰も楽しんでないし、時間の無駄だと感じることが多く、耐えられなくなった俺はあるときからいつもゲームを用意することにした。そして、それは高校時代には当然のように日常であったわけで、さらに先にかえればそれは治の影響である。そう考えると自分が彼の影響を大きく受けすぎている気がしてまったく腹立たしいのだが。
「ああ、持ってきてるよ」
そういって察し良く三階まで持ち込んでいたカバンからトランプの二倍ほどあるサイズの箱を取り出す。
「お、サボタイアか」
「そう、お邪魔者。これはみんなやったことあったっけ?」
一行の中では、浮田のみやったことがなかった。
「お邪魔者(Saboteur)は、鉱山をテーマにしたボードゲーム。作者はベルギー人の、」
「wiki田はいいから、俺が簡単にルールを説明して一回デモでゲームしようか」
「じゃあ私は知ってるから」と柿崎は甲斐甲斐しく皆が食い散らかした食事の片づけを申し出る。
五人になったその場で、皆にも復習を兼ねて説明をする。
簡略的に説明すると、プレイヤーが金鉱掘りになって金塊を見つけるゲームだ。カードを使ったゲームでスタートカードと横に七枚空けてゴールとなる金鉱カード一枚と外れカード二枚を伏せて配置し、プレイヤーは毎ターン一枚ずつ手札の道が描かれたカードを置いてゴールを目指す。しかし、金鉱掘りの中にはお邪魔者の役割を振られた者が一から二人おり、お邪魔者は自分がお邪魔者と悟られぬように金鉱掘りの妨害をする。道カードの他にも道具を壊すカードや道を破壊するカードなども存在している。最終的に山札と手札がなくなる前に金塊にたどり着けば金鉱掘りの勝ちで金塊は山分け、辿り着けなければお邪魔者が総取りとなる。
「これを三回繰り返してトータルスコアで競うんだけど、デモでとりあえず一回だけやってみようか」
単純なゲームなのですんなりとルールを把握してプレイすることができた。お邪魔者がランダムなので浮田にお邪魔者がいかないかだけが不安だったが、治がひいたようで無事、金鉱掘りの勝ちとなった。
「さて、それでは本番な訳だが、カッキー始めるよ」
と、離れていた柿崎も呼び戻し、六人になってゲームを始める。
お邪魔者のいいところはルールがシンプルは勿論のこと、持ち運びに便利なところと人数に自由度があるところだ。ボードゲームには人数指定があるものが多く、その人数ちょうどでないと遊べないものも多い。その点、お邪魔者は四から八人くらいまでの幅で対応することができる。逆に難点としてはゲームスペースを広くとる点とトークの絡む要素が多いゲームだという点だ。誰がお邪魔者か疑心暗鬼を生みつつするこのゲームは基本的に他人を疑ってかかるしかない。ゲームだと割り切って楽しめるなら良いのだが、自分が疑われること、疑われ続けることに耐えられないタイプの人間も存在しており、そういう人に対して、ルールだけで戦うゲームじゃないお邪魔者は不和の原因にもなりかねない。
しかし、臆することはない。
だいたいボードゲームなんてものは煽ってなんぼのものである。
ゲームが始まったら、皆、熱中した。始めは多少他人行儀だった治も慣れてこれば普段の毒舌も回りだし、最終的な勝率としては多分、治が一番だった。次に強かったのは小鹿だが、それは単に酒が入っていなかったからだろう。
白熱し続けること数時間、休憩といって人が抜けたりもしたが、これほど長い時間、同じゲームを続けられたのは珍しかった。
「おっと、もうこんな時間じゃないか」
小鹿がスマホで時計を見ていう。
俺も釣られて自分のを確認したがもう七時を回っていた。
誰が気を利かせたのか、気が付けば部屋の電気も点いている。
「えー、まだ早くないか?」
「何言ってんだ。そろそろ帰らないと家に着く頃には夜中になっちまうよ」
言われてがさごそと動き出すがここからが長い。やれ荷物がないだ、やれ片付けがしていないだの、いい加減面倒になったのか帰ることに否定的な意見だった灰田が片付けは全部やると言い出す始末。そこから、さらにやれトイレだの言い出し結局、畝葉邸を出る頃には八時手前になっていた。
慌てて皆を畝葉邸から追い出すと
「じゃあ帰るからな。またな」
と小鹿が半ば叫ぶように三階で片付けをしている灰田に声をかけ、見送りを待つことなく、車に乗り込んだ。
出発した車の後部座席から畝葉邸を見ると、駐車場上部のダイニングと二階のリビングに電気が灯っていた。
一行は一時間ほど車を走らせ、人里に下りるとファミリーレストランで晩ご飯を摂り、そこからまだ電車はあるというのに小鹿はわざわざ、それぞれの家へと送ってくれた。
レディファーストで最後になったのは俺と治。治は我が家で一緒に降り、そこで別れた。時刻は日付が変わる寸前だったと記憶している。
仕事中、スマホに母親からの急に電話がかかってきたのは、それから六日経った月末の金曜日、午後三時くらいのことだった。
「仕事中だと思うんだけどなんか警察の方が来てて話がしたいって」と電話口で伝えられ、最近、警察のお世話になるようなことしたかしらん、と頭を捻るが何も出てこず、三十分くらいで帰るとだけ伝えると、上司に話に行った。
「なんだお前。人でも殺したんか」
と定型の冗談を言う四十代の上司。殺すなら真っ先にお前を殺すわ、とはさすがに口には出さず、そういうことで今日はフレックスで帰らせてほしいと告げる。普段からたっぷり残業はさせられているので、ここで減らしたところで文句はないだろう。仕事は残っているが終わらせたら終わらせたで次の仕事が入り、自分のトータルの仕事量が増えるだけで無理に今日終わらせるメリットなどない。理由をつけて帰れるなら帰った方が得に決まっている。
上司の許可を取り付けると飛び出すように会社を出る。
ところで世間ではプレミアムフライデーというものの存在がまことしやかに囁かれているらしい。俺の予想だが、口裂け女とかその類だと思われる。
家に帰ると玄関先に母親と二人の男性の警察官が立っていた。背の高い何かスポーツでもやっていそうなのと、背が十人並みで眼鏡をかけたこと以外に特に特徴のないのだ。話を聞くと刑事らしい。そのへんの詳しい区別はわからないが、ドラマのように警察手帳を見せてもらった。
「昨日、灰田家の別宅にて灰田雅紀さんの死体が見つかりました」
ノッポが喋った。灰田家の別宅というのは畝葉邸のことだろう。
「灰田が死んだんですか」
「はい、そういうことです。死体は一階の鏡の部屋で発見されました」
死因は胸を包丁で一突きされたことによるショック死。発見の状況からして自殺の線が濃厚であるが、遺書が見つからなかったことから一応、他殺の線も疑っているという。
死亡推定時刻は発見が遅かった為、正確ではなく、土曜の午後四時頃から日曜の午前四時頃と考えられている。
「でも俺があの家を出たのは八時頃ですよ。正確に言うのであれば八時を回ってはなかったです」
「なるほど、では、最後に被害者を直接見たのはいつになりますか?」
質問は眼鏡が担当のようだ。
俺は回想する。三階で散らかした食器やらを淡々と片付けていた灰田は二階に降りてきてはいない。一方、お邪魔者を片付けた俺はついでにとトイレに行った後、カバンを持って二階に降りたのでそこで見かけたのが最後だ。そして、リビングで帰る準備の遅い女性陣を待っていたので最後に目にしたのは七時半ということになるだろう。
「なるほどなるほど、比較的早いですね。ちなみに他の人達が最後に三階に上がったのはいつぐらいかわかりますか?」
二階では俺よりも先に準備を終えてソファに深く沈んでいた治、そして、俺の次に降りてきた小鹿、そして、最後に二人まとめて降りてきた柿崎と浮田。
「だと思います、多分。いや、でも小鹿は二階に降りてきたあとまた一度三階に引き返したような、すいません、なにぶんバタバタしていたもので。でも治、じゃなくて橿井は私とずっと喋っていたので間違いないです」
「ありがとうございます。他の方との証言ともだいたい一致しているので間違いはないでしょう」
「この質問っていうのはあの僅かな時間に灰田を殺したのではないか、ということですか?」
確かに、帰り際、灰田は俺達の見送りをしていない。だから、リビングで俺と治が談笑しているときすでに殺されていたのかも、
「いや、そうではないんですが、先にこちらの質問をすませてもよろしいでしょうか」
「あ、はい。もちろんです」
俺の早とちりか。
「あの家の鍵はどなたが持っていたかご存知ですか?」
無論、灰田本人だろう。しかし、見てすらいない。
「なるほど、ごもっともです。次に、包丁ですが、その日、触りましたか、あるいは触ったと思われる人はいましたか?」
矢継ぎ早に質問が飛んでくる。しかし、これはむしろ、先入観を与えずに話を聞き出すという作戦なのだろう。こちらからの質問には後で答えてくれればよかろう。
料理は畝葉邸に着いたときにはすでに出来上がっていた。だから触った人はいないと思うが見ていないので実際はわからない。しかし、俺は触っていない。
「なるほど、ごもっともです。じゃあ、帰るときに鏡の部屋の電気が点いていたか覚えていますか」
口癖になっているのだろうが、この眼鏡刑事はなるほどと言いすぎている気がする。何も喋らないよりマシなのかもしれないが耳につく。
「帰り際に見た時は点いていなかったですね」
「それは確かですか?」
「はい」
以上で質問は終わりらしい。
そこから話を聞いたことをまとめると、まず灰田が家へ帰って来ず、二、三日くらいのことなら相手も子供じゃあるまいし気にしないところだが、会社も無断欠勤になっているという連絡もあり、灰田の両親も心配になって母親が畝葉邸に行ってみると鏡の間で灰田の死体を発見した。そのとき、リビング、ダイニング、及び、鏡の間の電気は点きっぱなしであった。灰田は仰向けになって倒れており、左胸、つまり心臓に包丁が突き立てられていた。包丁は前々から畝葉邸にあったもので、それからは灰田以外の指紋は発見されていない。
次に死亡推定時刻だが発見が遅く、すでに死後硬直も溶けはじめていた。消化状態も常に何かを昼から夜にかけて、常に何かをつまんでいた状態なので、諸々の要因から土曜午後四時から日曜午前四時とされている。
発見時、畝葉邸の鍵はかかっていたが、あの家はオートロックになっていたので、何もせずに家を出るだけでこの状態を発生させることはできる。そして鍵は灰田のポケットから発見されている。
また、最後に生きている灰田の姿を見たと思われるのは浮田の七時四五分頃、小鹿は一度は三階に戻ったものの灰田の姿は見留め、四十分には二階にいたという。この辺はだいたい俺の記憶とも一致している。
そして、鏡の間の電気は運転手である小鹿は振り返ることができず見ていないそうだが、柿崎、浮田ともに点いていなかったと証言している。電気が点いていなかったということはこの時点ではまだ殺人が実行されていなかったということだろう。
「つまり、これが他殺だと考えた場合、犯人はまず私達が遊んでいる間にタイミングを見計らって畝葉邸の鍵を盗んでおき、自宅に帰った後、再び、畝葉邸に引き返して、盗んだ鍵で侵入し、灰田を鏡の間で電気を点けたまま殺し、鍵は灰田のポケットに突っこんでそのまま逃走した、ということになるわけですね」
この辺から畝葉邸まで寄り道をしなければ車で二時間強、一番最後に家に着いた俺が一二時なのだから畝葉邸に着くのは二時過ぎ、十分に間に合う計算になる。
「そうですね。他殺で考えた時は我々も大体同じような推理になります。そして、鍵は実際はわかりませんが、普段はリビングにほかってあることもあったとのことなのでそうであれば盗むのは容易かったでしょう」
そうすると次に考えるべきは車が運転できたかという点と車を所持していたかだ。
小鹿は車を持っていて運転可能なのは明白だ。そして、俺。車は所持している。そして、酒を飲んでいたとはいえ大分抜けていたし、飲酒運転が違反だとかそういうことは今、関係はない。運転の可否だけが重要だった。あとのメンバーも運転の可否に対してはどっこいだろう。泥酔している様子はなかった。治は車を所持していないが家族が持っている。柿崎と浮田の事情までは存じないが、免許は持っていたはずだ。
「車に関しては浮田さんは自家用車を、柿崎さんは自分ではなかったが家族と共用のものはあったそうです」
そうすると条件はみな平等と言ってよいだろう。家にいたかどうかというのは家族の証言だがこれは当てにならないと聞いたことがある。
「夜中にエンジン音があったかどうかとかは」
「調べてないです。自殺の線が濃厚ですし、わざわざ調べるかどうかも怪しいです」
そういうものなのか。遊んでいたときの灰田は特に自殺をしそうな素振りもなかったと思うが、俺は久々に会うものだし、心の中まで覗くことはできない。
「あの、これって私が一番最後ですか?」
「いえ、この後の橿井治さんで最後です」
そういうと、それが合図になったのか、これ以上聞くこともないと判断したのか、俺に礼を述べ、二人の刑事は去って行った。まだ四時半にもなっていない。
『あとで行くから警察帰ったら連絡くれ』
と治にメッセージを送る。まだ流石に警察は到着していないだろうから、何のことだと騒いでいるのかもしれない。
いや、まだ普通は会社か。しかし、世間ではプレミアムフライデーというものの存在がまことしやかに囁かれているらしい。俺の予想だが、ツチノコはいてほしいと思う。
<登場人物>
畝沢 一平:主人公。俺。
橿井 治:高校時代の友人。
灰田 雅紀:大学時代の友人。被害者。
小鹿 荘二:大学時代の友人。運転手。
柿崎 景:大学時代の友人。カッキー。
浮田 翔子:大学時代の友人。wiki田。
畝葉 逗柳:SF作家。畝葉邸の元持ち主。
※畝葉逗柳は実在の人物ではありません。
以上で推理に必要な情報は提示してあります。
動機の面から推理するのは不可能かと思います。(描写不足で申し訳ありません)
犯人、及び、証拠あるいは証拠を導き出せる情報をお当てください。
解答篇
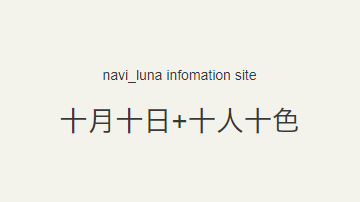

コメント