
これは私の―――――物語。
「遅いっ」
そのとき私、明日葉恋子(あしたばこいこ)は苛々していた。事情を説明する前に言い訳させてもらうと私は生来、怒りっぽい人間であるというわけではない。どちらかと言えば温厚で、品行方正容姿端麗、明朗は微発といったどこにでもいる平凡でかわいい女の子だ。
そんな私がこんなにも苛立っているというのには訳がある。真夏の日陰の少ない駅前で待ちぼうけを食らっているのだ。
現時刻は十四時。待ち合わせの時間は十二時半。
遅れてはならじと十二時までやっていたバレーボール部の午前練が終わった足で慌てて来たというのにこの有様である。ついでに言うと待ち合わせ時間で察しているかもしれないが、ランチは一緒に食べようね☆などとのたまう親友のセリフを鵜呑みにした哀れな私はしっかり運動した健康人間の為、空腹に悶えている。
「あいつ、来たらただじゃおかねえぞ」
この駅の周りには何もない。食事処はおろか、コンビニまでも歩いて五分はかかるという劣悪環境下にある。その為、少し動いた間に相手が来てしまったら申し訳ないと思って健気に待つ私は生真面目であり友達思いである為、軽食を取るタイミングまでも逃しに逃し、時すでに遅し、お腹と背中に間に余分な肉がないことが自慢のスレンダーな身体を恨めしくも思いつつ、いや、これは恨むまい、日常的なたゆまぬ努力の結晶であり、それを否定することは自分の美しさに疑問を持つことと同義であり、豚のようにぶくぶく肥える我が担任教師と自分が同一化してしまうということだ、それほど嘆かわしいことなどない。
それにしても遅い。
メッセージを飛ばしても、返事も既読もつかないし、電話を何度かけても出ない。
来ないにしてもせめて連絡が欲しいと明日葉は切実に願った。
そうすれば、その時間から計算してコンビニまでかけていくこともできたし、はじめから一度家に帰ることだって可能だったはずだ。
明日葉の白魚のような肌がじりじりと焼ける。
もしかして、事故にでもあったのか、という可能性がここまで待ち続けて初めてチラリと脳裏をかすめたがすぐに否定する。そんなわけはない。どうせ、寝ているだけだ。私は彼女を信用している。
「あー、むかつく」
私は足元に転がっていた石を力任せに蹴り飛ばした。
そう、どちらかと言えば事故にあってしまったのは私の方だったのだ。
それは大層陳腐な始まり。
「いってぇな」
しまった、と思った時には遅かった。どうせ、もう蹴ったあとなわけですし。
物理法則に則った石の意志はそばにいた少々ガラの悪そうな男性二人組の内、背が低く頭の悪そうな方の左太ももに当たってしまった。訂正しよう。少々ガラの悪く両方とも頭の悪そうな男性二人組の内、背が低い方に当たってしまった。
「ご……ごめんなさい」
咄嗟に謝る。脊髄反射だった。本当なら心底、他人になど頭を下げたくないと常日頃から思っている私ではあるものの、流石にこれは一方的に私が悪い。それぐらいはあとから理解が追い付いてきた。ならこの脊髄反射くらいは、まぁ許してやっても良かろう。悪いことをしたら謝るのは人の道義だ。弁えて遠慮深い私は最高に偉い。
「いってぇな、おい。お前、謝罪が足りねえんじゃねえのか」
ちなみに背が低いといったが私よりは目算二、三センチ高い。
「申し訳ありませんでした」
殊勝な私は素直に腰を折り頭を下げる。
「違うだろ、おい」
「じゃあ、ええっとバンドエイドならありますけど」
たしか、財布の中にこの前、束で入れたはずだ。
「なんで打撲なのにバンドエイド張るんだよ。常識的に考えておかしいだろ」
ここまでの会話で初めてでかい方が口を開いた。そして思う。確かにそうだ。実はでかい方はそれなりには賢いのではないだろうか。となると訂正する意味はなかったようだ。
「ちがうだろ、もっとあんだろ、ねえちゃん」
誰が、お前らのねえちゃんだ。どう見ても年上だろうが。ここはキャバクラか。
「石が当たったところをなでなでして痛いの痛いの飛んでけ、してくれるとかさぁ」
キャバクラか。
「普通に嫌ですけど」
素直で性格が良く物わかりの悪い優等生で学校では通っているこの私だ。
「んだと、そっちが怪我させたんだろうがそれぐらいいいじゃねえか、ちょっとくらい可愛いからって調子に乗ってよぉ」
ちょっとではなく大いに可愛いのだが、それは口に出さないでおこうと思う。照れ隠しかもしれないし。
「だから、謝ってるじゃないですか。あと、ちょっとじゃなくて私はとても可愛いんです」
「うるせぇ」
ごもっともな意見だとこの状況を俯瞰してみている自分が遥か上空に存在した。
「ねえちゃん、さっき見てればずっと一人じゃねえか。侘びの代わりに俺たちとお茶でもしようぜ」
そういって、強引に腕をつかんできた。チビの方が。
「嫌です、離してください」
さっきからと言っていたがそんなにも私のことをちらちらと見ていたのだろうか。美しさというのは時として罪なものなのだなぁ、と感慨にふける余裕はちょっとないようなので後回しにするとしよう。
「いいじゃねえか、侘びの代わりにお茶でも一緒に啜ろうぜ」
ノッポが話に混ざってきたが、そもそも私にはノッポに詫びる筋合いはない。それに喋っていることがチビとほぼ一緒だ。いや、啜るとか言い出してるあたり、より低俗だともいえるし、何より頭が悪そうだ。
「やめてくださいって言ってるでしょ!!!」
そう言って、私は腰にぶら下げたうまっすホルダーからうまっすを取り出し、眼前に翳す。
うまっすを視界にとらえた瞬間、二人組は一瞬たじろぐ。
「てめぇ、とくうまァーか」
口をそろえてそう言った。
今や、全世界にとくうまァーは六十億いると言われている。こと文明の進んだこの日本でその普及率は実に九八%に及ぶと言われ、生まれてきた赤ん坊が初めて口にする言葉はママでもパパでもなく「とくうま」だということもざらである。
そんな超とくうま時代に、とくうまァーか?という疑問を抱くこと自体がことさら不自然だとすら思われる。良心的に解釈した場合、恐らくはとくうまァーであるのはほぼ間違いないことだとわかってはいつつもここで「とくうまァーか」と言った方がセリフ切れが良く、場面が引き締まるという判断のもとから口に出たセリフだろう。
「とくうまカードをだされちゃあ仕方ねえな」
そういうとチビもうまっすホルダーからうまっすを出してきた。
「じゃあ、ねえちゃんが勝ったら全面的に許す、でも負けたらなでなでして痛いの痛いの飛んでけ、した後、お茶を一緒に飲む」
「いいだろう」
よく聞けば、悪いことが二つセットになっているような気もするが私には自信があった。
学校のとくうまカードの成績ではいつも一桁な私だ。このままいけばあのザガプロ大学にだってとくうま推薦で入れると先生達からも期待されている私がこんなところで、
「ただし、オレ達は二人だ」
気づけばノッポも手にうまっすを持っていた。
「な、そんなの不公平じゃ」
「何を言ってんだ。冷静に考えてみろ。そもそも悪いのはお前の方だぞ」
冷静に考えるとそうだ。自分が被害者な気がして来ていたが確かに私が加害者側だ。
「じゃあさっさと始めるぜ」
仕方がないと腹を括り、二人と共に私も高らかに宣言をあげる。
「「「トリプルシャッフルルールによりお互いのうまっすをトリプルシャッフル」」」
こうして、戦いの火蓋は切って落とされ、
「ちょっと待てぇええ」
突然、背後から声がした。圧倒的不利な状況だとしてもファイトの始まりに昂揚しないとくうまァーはいない。それに水を差すとはよほど重要な要件でない限り許されることのない所業だ。
無視してやるのも可哀想ではあるので、振り返ってやるとそこには腕を組み仁王立ちした青い服を来た美形の少年が立っていた。年は私よりも僅かに上だろうか。大学生ぐらいに見える。
「話はよくわからんが一対二なんて卑怯だぞ、オレが加勢す」
「うるせぇ、オレのターン、先行はドローすることができない。手札から空想具現化魔法カード【侵禁校則】を発動」
【侵禁校則】(ま)このとくうまファイト中、勝手に外部の者がファイトに乱入することはできない。
「しまった……」
チビが発動したカードは今この場面において、最も効力を発揮するカードだった。
「なんてピンポイントなカード、あまりにもとくうまらしいカード。だが、カードの効果は絶対だ」
青服はカードに従うほかない。しかし、そもそも乱入すること自体がマナー違反だし、場面が場面とは言えど、全部自分のカードでできたうまっすで参戦するのは卑怯だ。
「仕方ない。オレは彼女のパートナーとして見守らせていただこう」
そういうとあっさり引き下がり、再び、青服は私の背後に立った。彼は一体何をしに来たのだろうか。
「それぐらいなら許してやるぜ。オレは【メグリベーグル】をためてターンエンド。さぁ、ねえちゃんのターンだ」
私のとくうまファイトには独特のスタイルがある。それはカードを信じること、それは即ちウマッスに祈りを込めるということ。
私は右手をうまっすトップに置き、無心になる。そして、祈りを込めて引き抜く。
「私のターン。ドロー」
後方に置いてきたカードを手首を返し目だけでとらえる。
引いたカードは自分の作ったカードではない。そして、その効果を呼んで愕然とした。
【寄生蝶グラファイト】(HP7/こ0/た2)このカードのこは自分のタッグのバトル場にいるモンスターと同じになる。
(これは……タッグ専用カードだ……)
慌てて、自分の手札にすでにあるカードの効果も確認してみるが同様にタッグと組むことで真価を発揮する効果だった。
「トリプルシャッフルではうまっす内の仲間のカードが二/三を占める。しかも、タッグ効果は一人側には効果を及ぼさない。あいつらタッグ慣れしてやがる」
青服はそういうと顔をしかめた。でもそれは普段、二対二でのとくうまファイトを良くやっているだけなのでは?などというのは野暮なことだと思い口をつぐんだ
そう、私は今、想像していた以上に圧倒的窮地に陥っていることに気付かされたのだ。
「【ダブルフェイスアナコンダ】で【般若老人】を攻撃、死亡だ」
もう何体目になるだろうか、私のバトル場のモンスターが大気へと消えた。
「くっ、私はベンチから【めくりめーこぶ】をバトル場に出す。そして、私のターン、ドロー」
【めくりめーこぶ】(HP9/こ6/た5)カード名を宣言し、うまっすトップをめくる。当たった場合、ためが全部たまる。外れた場合ずっと攻撃できない。めくったカードは墓地へ。
勝負が始まってからもう数ターンが経過した。残うまっすは明日葉二枚に対し、チビ・ノッポ共に三枚。
二対一にも関わらず残りうまっすの枚数はほぼ均衡を保っているのは明日葉の類まれなるとくうま力の賜物であろう。しかし、それでも数の暴力には勝てず、じわりじわりと劣勢に追い込まれていた。
そもそもが不利な状況である。一瞬でも気を緩めば戦況は一気に崩れてしまうだろう。
「君、全体をもっとよく観察しろ」
背後から声がした。青服だった。
「ここまで見ている限り、君は非常に優秀なとくうまァーだ。センスもいいし、勘所も悪くない」
褒められるのは嬉しいが、今は喜んでいる場面ではない。これが学校の授業だったらどれほどうれしかったことか。
「が、その一歩で勝ちに対する貪欲さが足りない。勝負に華やかさを求めすぎている」
ん?意味が解らなかった。盤面の美しさ、論理の正しさ、タイミングの選び方。それが今までの私のとくうまカードの全てであった。それが否定されるとはいかなることか。
「それの何が悪いんですか」
劣勢と緊張感で焦り冷静を欠いた今の私の頭では害意のある言葉の意味をうまく処理しきれない。絶望感というフィルターを通し私は私の全てがぐちゃぐちゃに踏みつぶされるような嫌悪感を感じる。
そんな私を知ってか知らずか、青服はそっと近づき耳元で囁いた。
「いいか、よく聞け。今は絶好のチャンスだ」
青服はバトル場のモンスターをこっそり指さし言う。
「自分の場、墓地、手札、そして相手の場、墓地を見ろ。これが君にとっての公開情報だ」
場には一枚、墓地が十枚、手札が二枚。相手は場がバトル場ベンチで二枚ずつ、墓地は七枚と八枚。
「すでに全カードの内、約七割が君の視認下にある。その上で、今のうまっすトップは君のカードだ」
私はうまっすトップを見る。確かに自分の使った牛乳パックの柄である。
「そして、その内、君のカードすでに十一枚消費されている。つまり、宣言を当てる確率は四分の一だ」
そうかもしれない。でも、それでは絞り切れていない。まだわからない情報が多すぎる。
「君は自分の作ったカードの裏面を覚えているかい」
青服はとんでもないことを言い出した。
「ま、まさか、それは」
私は少なからず動揺する。だって、それはあんまりだ。
「シッ、静かに。あとあんまりうまっすトップを凝視するな意図がバレる」
とくうまカードというのは全てが手作りのカードである性質上、マークドが容易い。というか、裏面が全て違うのだから覚えようとすれば覚えられて当然だ。だが、それは同時にとくうまカードを楽しむという観点から一般にはタブー視されている。あくまでそういうことは意図から外してファイトするのがとくうまカードをやる上での最低限のマナーなのだ。
「思い出せ、裏側を、うまっすトップのカードがなんなのかを。そしてここからが重要だ。まるで勘で当てたように演技しろ。プロとくうまァーってのはみんな名俳優だ。奴らは自分のカードはおろか、一度でもメディアに露出したカードの裏面をすべて覚えてる。でも知らないふりをしているんだ」
そう言われても急に思い出せるものではない。しかし、しかし私なら。
「最強とくうまァーのファイトは常に必然、ドローカードさえもとくうまァーが想像する」
私は思い出す。牛乳パックを空けた時、何を思っただろうか、はさみを入れた時。どんなカードを作ろうとしたのだろうか、隣のカードはどんなかーどにしたのだろうか、このカードが一体何なのか。
「【めくりめーこぶ】効果」
私はすべて思い出した。このカードがなんなのかを、そして今まで作ってきた数千数万のすべてのカードの裏側を。
「えーっと、残りの私のカードが【星緑アリス】と【カーリーヴィジョン】と【ゆかいさらまんどら】とあとはえっとー……そうか。決めました」
私は朝ドラ女優張りの演技を見せ付ける。つもりだが。
「宣言します。うまっすトップは【スワン懐石】!」
そういって勢いよくカードをめくる。
カンコーン。
そう、それは間違いなく【スワン懐石】だった。
「やったー。宣言成功です。【めくりめーこぶ】のためがたまります。バトル入ります。右の方の【カブトリゲーター】を攻撃」
ためがたまり、一瞬の内に臨戦状態に入った【めくりめーこぶ】が【カブトリゲーター】を覆う。ノッポのバトル場のカードは霧散して消えた。
「けっ、運のいい奴め、ベンチ出して、オレのターン、ドロー」
私はこのファイトが始まって初めて楽しいと思った。そして、プロとくうまァーはこうやってファイトをしていたのだ。と、そこで心のどこかで何かがひっかかる。
彼は今、プロとくうまァーといった。じゃあ、まさか、彼もプロとくうまァーなのだろうか。
いやいや、まさか。こんなところに不意にプロが現れるだなんて、ありえない話だ。
プロとくうまァーといえば世界六十億の上位百名しか名乗ることの出来ない狭き門だ。それがこんな片田舎に現れるなど到底思えない。
ごちゃごちゃと気思案している間に気が付けば、敵のターンも終わろうとしている。ノッポもチビも【めくりめーこぶ】を倒すことはできなかったようだ。
私のターンがやってきた。さぁ、と勢い込んでドローをしようとするその手が固まった。
先ほど、カードをめくったせいでうまっすは最後の一枚だった。そして、さっき叩きこまれたテクがすでに染み付いてしまっていた。
(このカードは私のカードではない)
濃縮還元なし100%ジュースのパッケージ。うまっすトップを見るだけでカードの内容を想像してしまう。
牛乳を飲まないからチビなのだと視界の左端をチラ見する。
しかし、仕方のないこと。これがとくうまだ。これとく。
「ドロー」
私は最後の一枚を引いた。
【スクランブル・タッグ】(ま)パートナーはうまっすから好きなモンスターカードを選びバトル場に出す。バトル場にモンスターがいる場合はそれを破棄する。
またタッグ用のカードだった。私は負けを確信した。
残りの手札も大したことない。【めくりめーこぶ】は強力なカードだったが、これももう最後の灯火に過ぎなかったというわけだ。
「いや、最高のカードをひいたぜ」
青服はそう言った。一体、何を言っているんだか、そもそも、彼が何の役に、
「そうか」
私、明日葉恋子の頭に電流が走った。
「私は【スクランブル・タッグ】を発動」
「なにをしている。それはタッグ用のカード、効果は発動しないぞ」
チビはそう私を指さし笑う。
「いいや、違うぜ」
青服が言った。
「彼女のパートナーはこのオレだ。勝手に乱入はできないかもしれないが」
彼は一歩踏み出し、私の横に立った。
「カードの効果なら仕方がないわなぁ」
そういうと腰で揺れるうまっすホルダーを開けた。
ごう、と音が鳴りどこからか風が吹いた。
彼の髪は優雅に舞い、ジャケットはぱたぱたと旗めく。
私は隣から今までに感じたことのない大きなプレッシャーを感じた。
そして察する、この人は今までに出会ったとくうまァーの中で一番強いと直感する。
これは格が違う、と。一生かけても勝てない、と。
彼はうまっすを左手で取り出すと両手を大きく広げた。
すると十五枚の夢の結晶はマジシャンがトランプを飛ばすが如く、それも延々と手の間の宙を移動する。

やがて、どういう原理かは全く分からないが、その中のカードが一枚だけ大きく空へ飛び上がった。とくうま力の高さが為せる技なのだろうか。
そして、彼はパン、と錬金術をするように手を叩くとその間には十四枚のカードがすでにおさめられており、時間が止まったようにゆっくりとうまっすホルダーに仕舞う。
やっとのこと落ちてきたカードを眼前で勢いよく音を立てて掴み取るとそのまま、身体を一周回転し、高らかに宣言した。
「オレは【正義のヒーロー】を召喚」
【正義のヒーロー】(HP1/こ1/た0)―――。
指に隠れて効果は見えない。
「なんだよ、こ1の雑魚モンスターじゃねえか」
ノッポが笑う。
「違うぜ、正義のヒーローは……大切な人を守る為なら誰にだって負けないんだ」
親指をずらし、隠れた効果欄を見せ付けた。
―――大切な人を助ける為ならば、こ+100、HPは無限になる。このカードはすべてのバトル場のモンスターに一度ずつ攻撃しても良い。
「オレにとっては世界中のすべての人が大切な人だ。よって、効果は適用される」
そして嵐のように勝負は終結した。
チンピラ二人組は逃げるようにその場を去った。
「ありがとうございました」
私は改めてお礼をする。
「いいってことよ」
青服は笑いながら答える。
そういえば、まだ、この人の名前すら私は知らない。
「あの、貴方は一体……」
「オレか?」
彼は両目を瞑り、しばらくしたあと開いて言った。
「オレの名前は神楽一太郎、全世界六十億のとくうまァーの頂点に立つ……」
これは私の―――。
「プロとくうまァーだ!!」
―――ヒーローの物語―――。
バァァン。
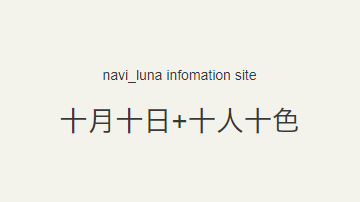

コメント