「ごめんねぇ、毎朝毎朝」
インターフォンを押すと、彼女の言う通り、昨日と同じように森島剣ではなく、その母親が出てきた。
「いえ、私が好きでやってることですから」
「そうは言っても、うちの子ときたら毎日全く進歩がなくって。まったく、このまま一生、朝起こしに来てくれるわけもないのに」
私は一瞬、どきりとする。剣との結婚生活を思わず想像してしまったからだ。いやいや、ありえない。私と剣は単なる腐れ縁なだけでそんな未来があるわけがない。大体、剣はモテるし、私なんてそこらへんの女子には勝てっこないんだから。
なんて一人で顔を赤くさせている内に、玄関の奥から「コラー、いい加減に起きろ剣」という怒鳴り声が響いてくる。
「うるせぇーなー」「親に向かってうるせぇとはなんだ。いいから早く着替えて学校行きなさい。迎え待ってるよ」「わあってるよ、ちくしょう」
ドアが開けっぱなしのせいで、全部の声が筒抜けだ。私はまた違う意味で顔を赤くする。私に、あんな風に剣を怒鳴ることができるだろうか……って違う違うそうじゃない。
私はただ今日は迎えに来ただけで、これからずっと迎えに来続けるなんてそんなわけないんだってば。
しばらく、待つと、寝ぐせの付いたまま、学ランを着崩して剣が出てきた。
「おはよ」
私は声を掛ける。
「ああ」
剣はそれだけ言うと、私なんかいなかったかのように歩き出した。
「こら、剣。いってきますは」と、また家の中から声がするが、当然のように無視をした。私は戸惑って、何故か代わりに「いってきます」と返事をし、先を歩いている剣を小走りで追いかけた。
「剣ちゃん、待ってよぉ」
私はぷんすか怒りながら、剣の隣に立つと息を整える。
「一人で先に行くんじゃ、迎えにいった意味ないじゃん」
「お前が勝手に迎えに来ただけだろ。俺は頼んでない」
「また、そういうこと言うー。私が迎えに行かないと剣ちゃん学校に行かないじゃん」
「いいだろ、別に。お前には関係ねぇ」
でも、裏を返すと、私が迎えに行きさえすれば、剣はちゃんと行くのだ。なんだかんだ言って可愛いところがある。
「まったくもう」
と一人納得し、鞄を剣の尻に叩きつける。
「いってぇな、なにすんだよ」
ふふふ、と私は笑みを漏らすと駆け出す。
「なんでもないよ。ほら、早くしないと遅刻しちゃうぞ」
私を追いかける足音が早くなる。素っ気ない振りをしたところで剣はやっぱり優しいのだ。
「今日はもう出かけたよ」
「え?剣ちゃんが?」
森島の母親はとんでもないことを言い出した。
「ええ、そうなの。一時間くらい前に物音がしたと思ったら、剣が出てったのよねぇ。でも学ランは着ていたから、学校に行ったんじゃないかしら」
「そうですか」
私は一瞬俯きかけたが、いやいやそうではない。剣が、一人で学校へ行く気になったことを誇らしく思うべきなのだ。
これで晴れて、私も剣の保護者としての任も解けたということで、実は寂しくなんて思ったりしていない。
それに……、いやいやそれこそ剣には関係のない話だ。
踵を返すと、一人学校へ向かう。
「あれ、今日は森島くんと一緒じゃないの」
昇降口でクラスメイトに声を掛けられる。
「うん」
「じゃあ、サボりってこと?やだやだ不良ぶっちゃって」
「剣ちゃんは不良じゃないよ」
「まぁ確かに喧嘩したりはしてないけどね。でもあんだけしょっちゅう学校サボったりしてたら立派な不良だとあたしは思うけどなぁ」
「違うよ。それに剣ちゃんは今日もう学校に行ったんだって」
「あれ?そうなの?」
彼女は目を真ん丸く見開く。
「へぇ、森島くんが一人で学校にねぇ」
私の方をチラチラ見てはにやにやと笑ってこっちを見る。
「な、何よ」
「いやいや、森島くんがようやく独り立ちしたかぁ、と感動してしまってね、ってあれ、でも」
彼女の視線が胸元辺りで止まった。
「森島くんの下駄箱、空だよ」
教室に行っても、剣の姿はなかった。
剣のいないこと以外は(剣がいないことは珍しくないのだが)、いつもと変わらず終わった一日だった。
授業を終え、夕方に一人歩いて校門へ向かうとそこに背を持たれかける長身の姿があった。
異様な圧があるのか、腫物を触るかの如く、皆がそこを避けている。
「剣ちゃん」
私は駆け寄った。
「よっ」
剣は無愛想ながらも返事を返す。
「もう放課後だよ。やっぱり、学校に来てなかった。剣ちゃんが一人で学校に行けたことなんて小学校のときから一度もないんだから」
剣は小さい時から何も変わっていないだけなのだ。小学一年の頃、私が風邪で休んだ時、「迎えが来なかった」などという驚きの理由で学校を休んだらしい。以来、何としても私を理由に休ませなどさせまいと心に誓い、その後、ずっと皆勤賞を続けているのだから、私の誠意には感謝して欲しい。迎えに行ったところでサボるときはサボるのだけれども。
「なんだよ。学校ぐらい一人で行けるわ」
「嘘ばっかし。じゃあ、明日から迎えに来ないんだからね」
「いいよ、来なくても。ったくいちいちめんどくせぇなぁ」
「本当にいかないんだからね」
私は怒っていた。じゃあ、一体、私の今までの人生は何だったのだというのだろうか。
自分の手元から巣立ったと思った雛が隠れていただけで、でももう餌はいらぬというのだ。
思わず、涙が込み上げてきた。それを決して剣には見られまいと回れ右をし、歩き出す。
「おい、ちょっと待てよ」
「うるさい、剣ちゃんなんて大っ嫌い」
「だから待てって」
剣が私の腕を掴む。振りほどこうとした刹那、剣が逆の手に見慣れぬ紙袋を持っていたのに気づく。
「これ」
剣はそっとそれを差し出すと私とは決して目を合わせずに言う。
「お前、今日誕生日だろ。だからやる」
そうか、剣は今日、この為に学校をサボったのか。
「あと、ごめん」
そういうと今度は反対に剣が逃げるように道路をを歩き出した。なんだなんだ愛い奴め。
私は途端笑顔になって、剣を追いかける。絶対逃がしてなるものか。
朝、起きる。
髪をとくと大きな髪留めで留める。
いい加減補修だらけだし、年相応でもないと周囲からは笑われるが、私にとってはこれじゃなきゃダメなのだ。
私はいつも早めに着くタイプなので、職場はまだ閑散としている。
マグカップにインスタントコーヒーを注ぐと自席に座り、始業までの時間に浸る。
「おはよう、ミボー。今日も早いね」
そう言って声を掛けてきたのは同僚だった。以前はそんなに早く来る方じゃなかったのに最近は早く来る。その上、デスクも離れているにも関わらず、わざわざ始業前の時間に私の元までやって来て話し込む。
多分、彼は私のことが好きなのだろう。
「でさ、今日の仕事ってのがさ、っとおはよう」
彼は勝手に隣の席の椅子に座っていたが、席の主が出社してきたので立ち上がる。
「おはよう」
私も隣席の同僚に朝の挨拶をする。件の彼は所在なくなったのか、もうちょっとここで話ができないかと思案したようだが、やがて諦めて自分の席に戻ってきた。
「あいつ、ミボーのこと好きだよ」
「わかってる」
そうわかっているのだ。
「ミボーは可愛いし、胸もでかいからモテモテだよね。私にも何人か分けて欲しいよ」
「その台詞。同性同士でも今どきはセクハラですよ」
「あ、ごめんごめん。でもさ、ミボーはあいつのこと嫌い?」
「いや、別にそんなことないですけど」
私はそっと髪留めに手を当てた。
「そっか、ミボーだもんね。そりゃ惚れた相手が悪いわ」
「いい加減わかってるんですけど」
そうわかっているのだ。
あの日を最後に、剣を迎えに行くことができなくなるなんて思いもしなかった。
交通事故だった。
夜、コンビニへ行こうとしたときに車に撥ねられたらしい。
学校には一人で行けないくせにコンビニには一人で行けたのだ。バカだなぁ本当に。
いつかの飲み会の席で私は、剣との関係を口走ってしまったらしい。その頃から渾名はミボーだ。未亡人のミボー。今では由来すら知らずにその渾名を口にする者も少なくない。不名誉な渾名だが、それだけに、自分には相応しい渾名に思えた。
今日も仕事を終えた。定時で上がると真っすぐ家に帰る。コンビニすら寄らない。寄ると轢かれるから。
ワンルームのドアを開けた。
「ただいま、剣ちゃん」
写真立ての中には、尖っていた頃の今思えば可愛らしい剣の写真が入っていた。
いつか、剣が迎えに来るまで、私は彼の影と共に生きていくのだろう。
もう私には迎えに行くことはできないから。
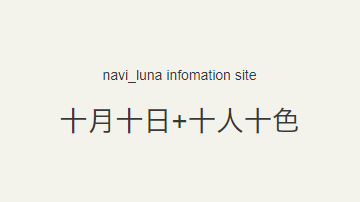


コメント